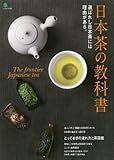【仙台】杜の都大茶会に行ってきました お茶もお菓子もうまいぞ!!!
5月下旬に仙台で開催された「杜の都大茶会」に参加してきました(一人で)。お茶の作法など微塵も知らない私ですが美味しいお茶と和菓子が頂けてすごい楽しかったです~、初心者でも気軽に本格的なお抹茶を楽しめる、とても素敵なイベントでしたよう(*˘︶˘*).。.: *♡
- 杜の都大茶会とは
- 最初は「織田流煎茶道」へ
- 織田流煎茶道のお茶とお菓子
- 続いて「遠州流茶道」へ、のはずが…
- という訳で勾当台公園のスタンド喫茶へ
- 気を取り直して茶席へ
- 杜の都大茶会の良かったポイント
- 公式パンフも面白い
杜の都大茶会とは

仙台の勾当台公園で初夏の恒例となっている杜の都大茶会。2017年で第21回になるそうです。
実は母が茶道を習ってたのでイベント自体は知っていたんだけど、「茶道?エッ着物無いし作法分からんし緊張する、無理」つって避けてたんです。
でも今回、母が「啜り煎茶ってのがめっちゃ美味しかった」って言うからどうしても気になって、一人で(!)いってきました。
会場は勾当台公園。朝9時半から開始らしいのですが、9時半に行った母によると「もう3席目だった」らしく。。。早いところは朝9時頃からやってるのかもしれません。
9時半に行った母は「まだ人もいなくて全然並んでなかった。人気の裏千家もすぐ入れたよ」と言っていました。
あ、茶会の料金は1席700円。前売り券を買うと、2席で1200円で購入できます!お得!来年は前売り券買おう…。
最初は「織田流煎茶道」へ
なお、私は昼の13時頃に参上。綺麗に晴れて暖かい日だったということもあり、かなりの人がお茶会に来ています。裏千家はもう、ほんとに、年末バーゲンセールのような黒い人だかり。各茶席は20~30分ほどだそうですが、裏千家は余裕で1時間以上待つだろうな、と思ったので今回はパス。
母が勧めてくれた「啜り煎茶」を楽しめる流派にいきます。それがこちらの織田流煎茶道です。
名前の通り、織田家(織田信長の兄弟・織田有楽斎)が始めた流派だそうです。今の家元で第16代だとか。茶道文化の歴史を感じる。。。
お茶会はテントの中で、椅子に座って行われます。なんか、思ったよりもカジュアルな席で安心しました。
茶道の作法や茶器、掛け軸、花などのお話を聞きながらお茶とお菓子をいただきます。
織田流煎茶道のお茶とお菓子

最初にお菓子。これは「萩の月」で有名な菓匠三全の練りきり。「天女の花(だったかな)」というそうです。甘さ控えめで上品な味。楊枝でサクサク切っていただきます。懐紙にそっと差し込まれた青いモミジに初夏を感じますね。白とピンクの花とのいろどりも綺麗。和菓子って美しいなあ…。
次にお茶。これが今日の目的、「啜り煎茶」です。なんと湯呑みの中に茶葉が入っていて、蓋をしたままお茶だけを飲むんです。
初めて見た。すごくない?おもしろくない?お茶の先生?も「うちの流派でも珍しいやつなんですけど~」と仰っていました。
お茶はズイエンという名前の玉露らしく、仙台ではリョッカテイというお茶屋さんで取り扱っているそうです。緑香亭…?どこだろう。お茶はググってみたらネット通販で取り扱ってるとこもあるっぽい。優しい甘みがあってとても美味しいお茶だったんだけど、ネット通販では200g辺り2000円ぐらいで売られてました。まああんだけの人数に出すお茶なんだから、ホイホイ高級なお茶っ葉を使うわけないよね…と納得。
でも普段玄米茶や煎茶ばっかり飲んでる私にはすごくおいしく感じられました。ブルジョワ…いえ、貴族の味がした。
ちなみに、この茶葉はそのまま食べることもできるそう。先生曰くポン酢を掛けて食べるのがお勧めとか。ホウレンソウみたいだな。
続いて「遠州流茶道」へ、のはずが…
流派とかわかんないし、2席目は直感でビビッときたところに行こう!と決めた結果、こちらの「遠州流茶道」に。
その決め手は、公式パンフレットの説明文。
ご機嫌よろしゅうございます。(中略)
流祖は徳川幕府の作事奉行であり、桂離宮や~(中略)美術工芸品の指導・鑑定に優れた才能を持ち、東洋のレオナルド・ダ・ヴィンチにたとえられております。
面白すぎるだろ。ウィトルウィウス的人体図ばりに両手掲げて期待しちゃう。
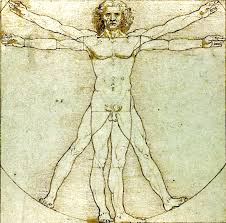
ただこちらのブース、1回の人数が少ないらしくて1時間近く待つことに…!
さっきのブースは20分ぐらいですっと入れたので、ちょっと意外でした。ヒィ。
という訳で勾当台公園のスタンド喫茶へ


あんまり知られてないんだけど、勾当台公園って売店・喫茶あるんですよ。
そば食えるんですよ。知ってました?スヌーピーのぬいぐるみとか、ちょっとしたオモチャとかも売ってるやで。
気を取り直して茶席へ
で、50分ぐらい待ってようやくテントへ。
みんなが着席したところで、「本日は野点風の~、お花は鉄仙で~」と色々説明してくれる。50代ぐらいの袴を穿いた男性が、神妙な顔で、しかし一つ一つの所作は丁寧にお茶を淹れてくれました。
お菓子はこちら。その名も「おとし文」。あの虫のオトシブミと、届かぬ恋心を認めて落とした「落とし文」を掛けているんだとか。日本語って風情があっていいですねえ。
鮮やかな青が、初夏の爽やかさを感じさせます。こちらも甘さ控えめ、こしあんたっぷりでおいしかったです。

お茶はお抹茶。苦くて、でも香り高くておいしかったです。さっきの啜り煎茶は器がこまかったから、こっちは飲みごたえあって良いですね。こちらの席も30分ほどでお開きとなりました。
*
杜の都大茶会の良かったポイント
★お菓子がおいしい
和菓子って芸術やな。日本の四季ってうつくしい。めっちゃうまい。
★お茶がおいしい
本題ここですよね。でも私お茶のお手前とかわからないんで何も言えないんですけど、とりあえずお茶めっちゃうまいです。すき。
★着物を見るのが楽しい
着物は何着見てても飽きなかったです。着物、帯、帯留め、髪飾り、下駄、etc...色の取り合わせ、柄の組み合わせ、人のを見ながらなるほどなーって思いました。着物って美しいねぇ。
公式パンフも面白い
ちなみに公式パンフレットには流派の説明が充実している他、
お茶の専門用語解説もあってなかなかおもしろいです。このお茶を飲んでお菓子食べてパンフももらえるならそこそこお得かも?
お一人様の参加でも全然大丈夫!なので気になる人は是非行ってみてください(*˘︶˘*).。.:*♡